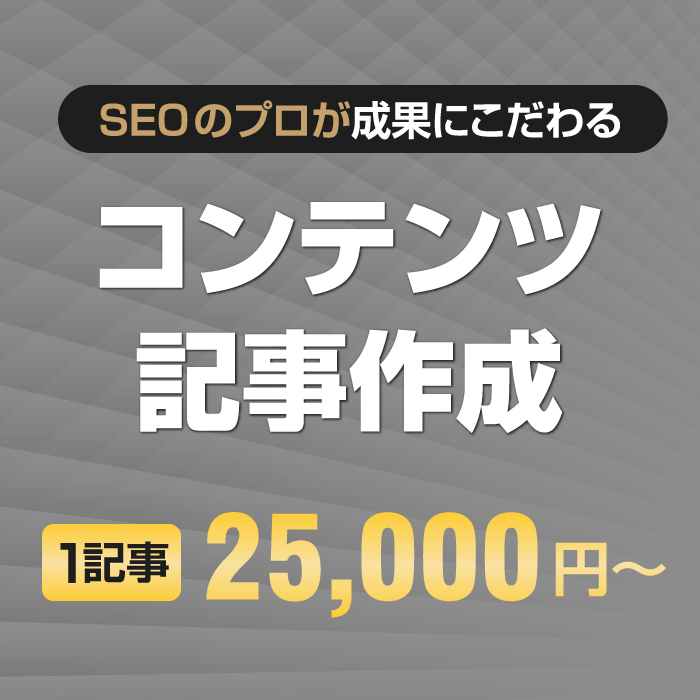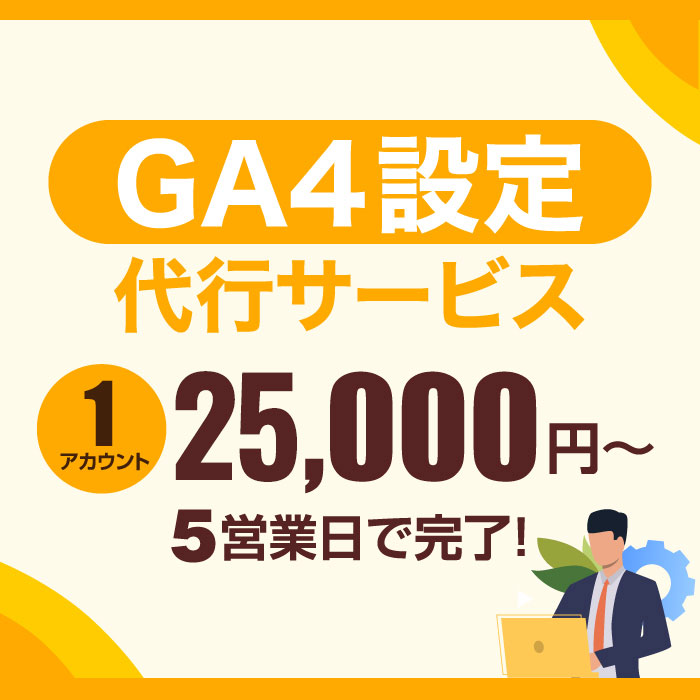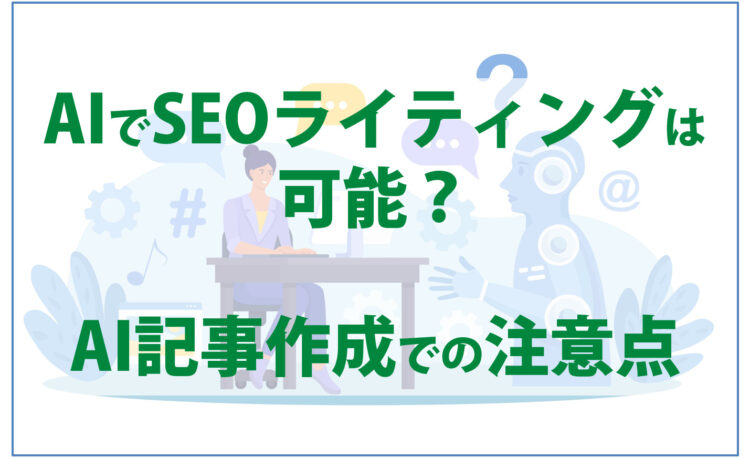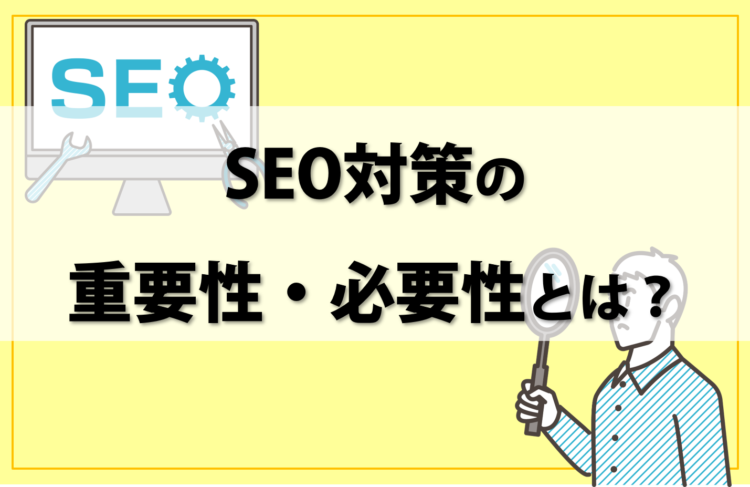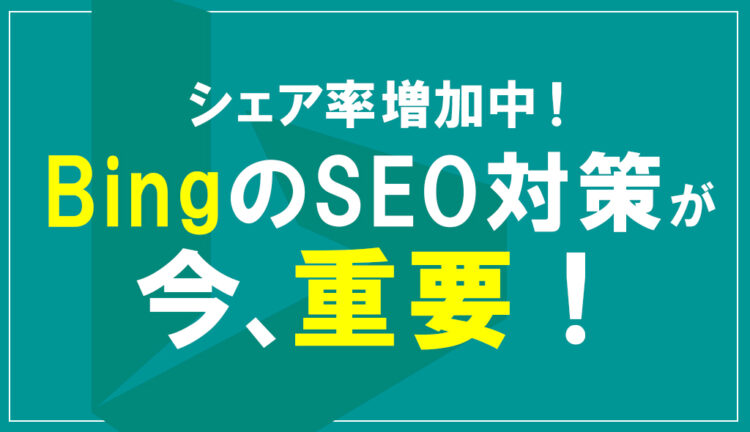プレスリリース代行サービス

![]()
報道関係者への情報発信
で新商品、新サービスの
メディア掲載
![]()
検索エンジン流入数が
増えるのSEO効果、並びに、
指名検索の増大
![]()
企業・採用
ブランディングへの
寄与
![]()
ソーシャルメディア
での話題拡散
![]()
メディア掲載情報を
営業資料へ記載、または、
HPへアップすること
による信頼度獲得
プレスリリースでよくあるお悩み

本来、プレスリリースとは、A4用紙2〜3枚にまとめる報道機関向けの企業ニュースです。
しかし、最近では、web上のプレスリリースサイトを経由して配信をする方法が主流に、、、
これまでの紙面にまとめていた文章をそのままweb上で配信しても読まれません。
ユーザーも報道関係者も情報過多な現代に「簡潔で分かりやすい情報」を求めているからです。
そこで、以下のお悩みが増えています!
web配信で効果の出るプレスリリースの書き方が分からない…
そもそもどの媒体でどう配信したらいいのかわからない…
書く時間が無いプロのライターに作成を依頼できたらいいのに…

web集客のプロがあなたに代わって原稿作成から配信まで
01
現役のwebマーケターが企画・構成
02
プロライターが原稿作成
03
短納期・低価格・縛り無し
必要な時だけご利用ください。
プレスリリース配信先は自由に選べる
発信する内容に応じて有益なリリース配信サイトをご紹介
『Good press』では、『PR-TIMES』での配信は必須と推奨しております。

プレスリリース配信までのフロー

プレスリリース代行3つのプラン
添削・リライトコース
1本 70,000円~
最短8営業日
- 初回ヒアリング30分
- ヒアリングをもとにいただいた原稿を添削及びリライト
- リライトした記事を提出
- 記事修正(1回まで)
- 記事の最終校閲
- 納品
- プレスリリースサイトで配信ください。
ヒアリングから執筆プラン
1本 100,000円~
最短15営業日
- 初回ヒアリング60分
- プレスリリース配信サイトご提案
- ヒアリングを基にタイトル・キャチコピー・構成案作成
- 構成案を基にお打ち合わせ30分
- お打ち合わせを基にプロのライターが記事執筆
- 執筆した記事を提出
- 記事修正(2回まで)
- 記事の最終校閲
- 納品
- プレスリリース配信作業代行
企画提案プラン
1本 150,000円~
余裕を持ったご相談を
- 初回ヒアリング60分
- リリースするべき情報と方向性のご提案
- プレスリリース配信サイトご提案
- 決定した情報を基にタイトル・キャチコピー・構成案作成
- 構成案を基にお打ち合わせ30分
- お打ち合わせを基にプロのライターが記事執筆
- 執筆した記事を提出
- 記事修正(3回まで)
- 記事の最終校閲
- 納品
- プレスリリース配信作業代行
※各メディア宛のプレスリリース郵送代行についてはオプションでご対応可能です。
※写真撮影や画像加工についてはオプションでご対応可能です。
Webコンサルタントと一緒に
“売れるホームページ”を制作しましょう!!

プレスリリースよくある質問
web集客のプロが、web配信に特化したリリース原稿を作成します。
検索結果に表示されやすい工夫やクリックを誘発しやすい工夫。PS、スマホ双方で読みやすい工夫などがなされた記事です。
はい!効果の大小は測れませんが、プレスリリース記事内にサイトのURLや製品ページのURLを設置することで被リンクを得られ結果SEO効果が得られます。
こちらは決まった頻度で行う必要はありません。配信したい内容があれば都度配信が最適です。また、同じ内容のリリースをタイミングを分けて配信することも効果的です。
ポップアップイベントなどの場合は、「開催決定時」「開催1か月前」「開催3日前」など少しずつイベントの詳細情報を公開していくことでユーザーの期待を掻き立てる効果もあります。
新製品発売の場合も同様、「〇月上旬発売!」「詳細のスペックを公開」「〇月〇日発売決定!販売価格を公開」などの段階に分けることができます。
はい!撮影内容や撮影場所によってお見積もりいたしますが、写真撮影:40,000円~、動画撮影:50,000円~ご対応可能です。
はい!ご要望に応じてお見積もりいたしますが、郵送用紙面作成およびデータ納品:20,000円~ご対応可能です。
必ず結果が出る!
“顔の見えるSEO会社”がコンテンツでアクセスアップをお約束します。
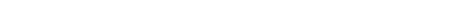
このウェブサイトでは、閲覧状況の把握や、お客様に合わせたコンテンツ、広告を表示するためにCookieなどを使用してパーソナルデータを利用しています。
第三者が提供するサービスのパーソナルデータ利用については「プライバシーポリシーについて」をご確認ください。
確認